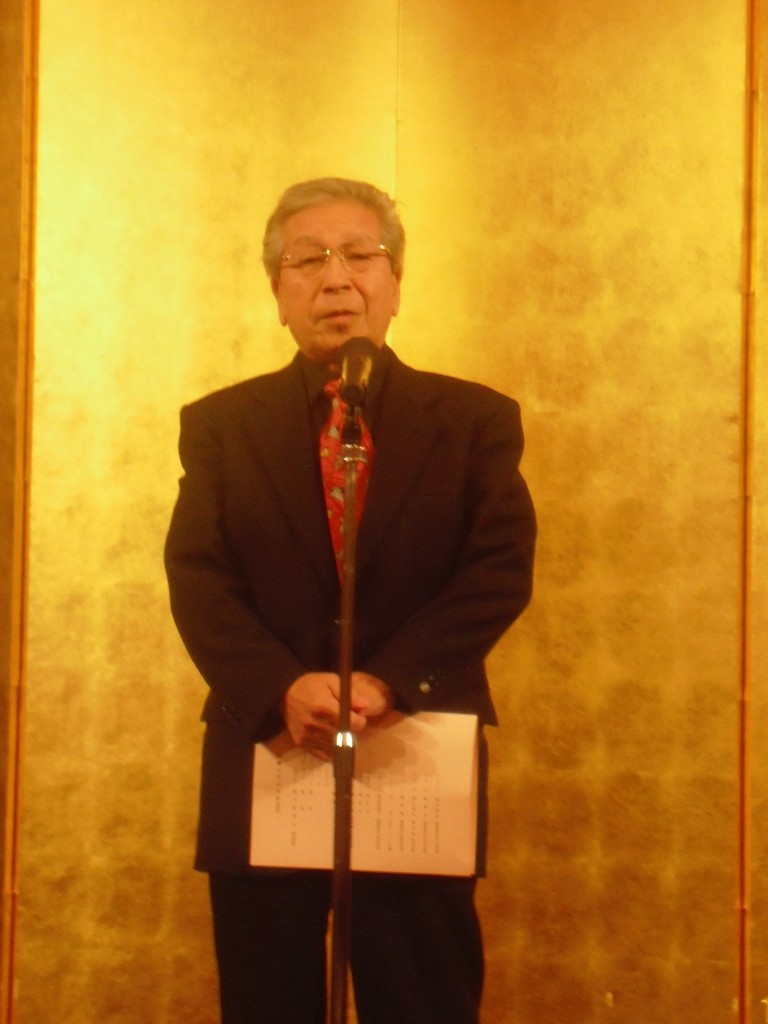官邸の後、経産省に藤木俊光経済産業政策局長、そのあと総務省に新田一郎審議官を訪ねた。藤木氏は富山県商工労働部長、新田氏は富山県経営管理部長などを務められた方で、その時からの知人です。お二人共、橘・佐藤氏同様国会開会中にもかかわらず時間を割いて頂き感謝です。
それにしても、局長や審議官ともなると個室が与えられ、10人程の会議ができるテーブルが配置してあり、応接セットがあり、専属の秘書がいるなど課長とは雲泥の差です。しかも感心したのは、約束した時間の2時間程前に秘書の方から私のケータイに会議が10分ずれたため、そのようにお越しください。との電話があることです。
私の感覚でいえば10分程度なら、私が行った時その旨話されれば良いと思うのだが、さすがと感心しました。お二人とは与党過半数割れした国会運営などの話しにも及びました。
写真は、官邸での反省から座って撮りました。藤木局長。新田審議官。
![250218122718704[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/02/2502181227187041-1024x759.jpg)
![250219113416615[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/02/2502191134166151-1024x759.jpg)
文科省友人との懇談会
18日夕、文科省友人と懇談会を行いました。これは平成16年から滑川市が文科省の25歳前後の研修生を2週間から3週間ほど、昨年まで21年間受け入れていました。しかし、新型コロナで3年間、東日本大震災で1年派遣が中止になりましたが、今日まで引き継がれ計17名を受け入れました。
それが15年ほど前「文科省ナカヤ会」を作ったから私が上京の折、集まろうとなり、年に1-2回懇談会を開いています。
平成16年初めて受け入れた1期生は現在文科省より山梨県教育長に出向している人や、スポーツ庁の課長或は各都道府県の教育委員会の管理職として出向している人、パリへ赴任している人など多彩な顔ぶれの集まりです。
それ故、全員が揃うことはむずかしいですが、常時8人前後集まり当日は国会開会中で答弁書作成準備などで突然の欠席者が出ましたが、和気あいあいの集いでした。
しかし、この青年たちが明日の文部行政を背負っていくことを思うと、頼もしくもあり、心もとない様に感じたりもする。人生のささやかな先輩として「官僚としての矜持を忘るるなかれ」かって遣隋使や遣唐使は、命がけで荒海を渡り隋や唐の律令制度や仏教や新たな文化を吸収し、「国つくり」に務めた彼等の「志」に思いを馳、公務員になった時の初心を忘れてはならない。と激励しました。
各人の近況を語り合いながら話しに花を咲かせました。また、各省庁にもこのような制度があるが、この様に一堂に会する機会があるのは多分この会だけだろう。とのことでした。名残を惜しみつつ再会を約し散会しました。
写真は、メンバーとの懇談会
![250218211801935[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/02/2502182118019351-1024x759.jpg)
![250218161006051[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/02/2502181610060511-759x1024.jpg)
![250218163200610[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/02/2502181632006101-1024x759.jpg)