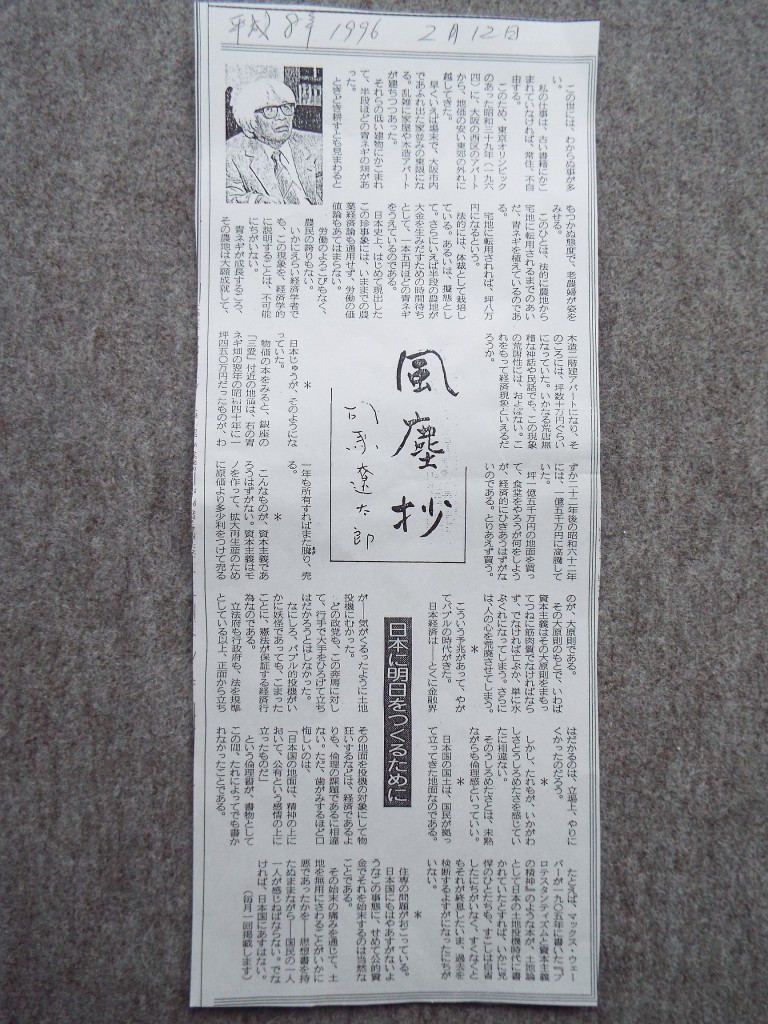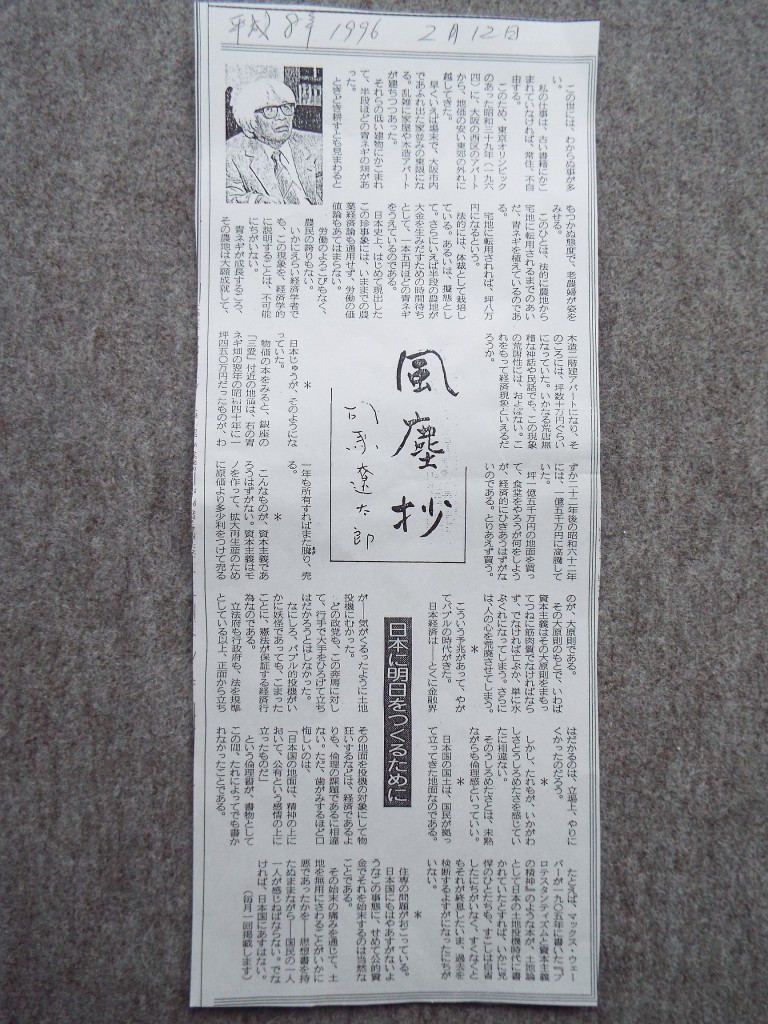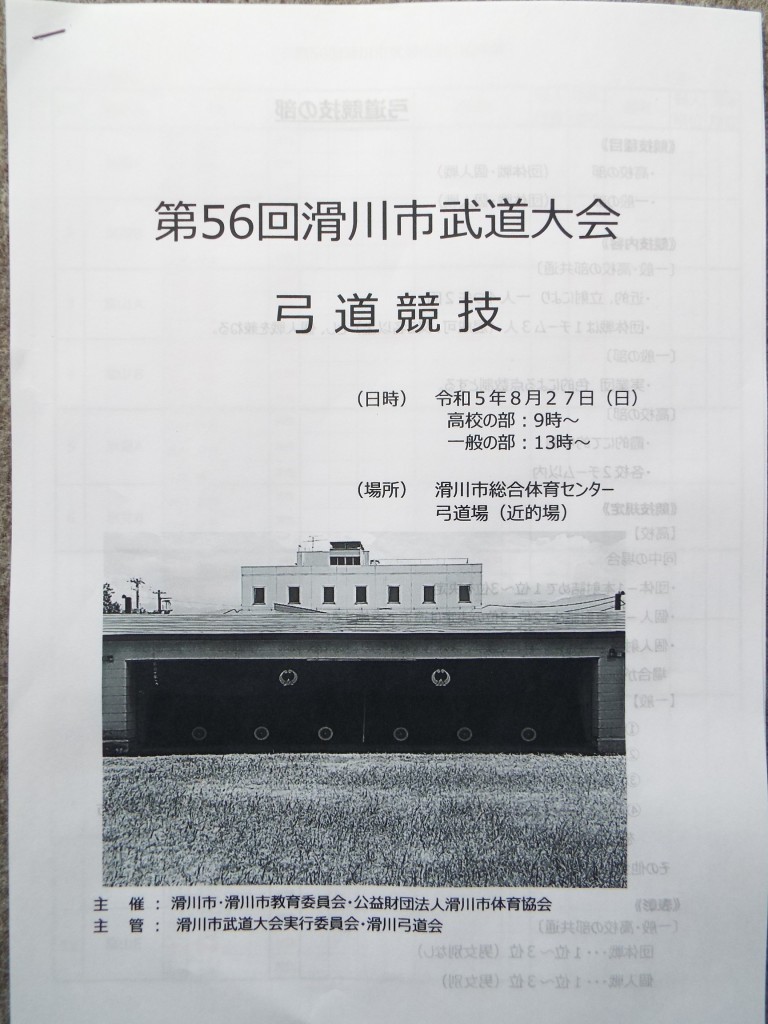9月20日、県は2023年7月時点の県内基準地価を公表した。同時に全国各地の地価の変動も公表された。
県内の基準地価は商業地で2年連続上昇、富山市がプラス1.9%で、10年連続の上昇、理由は新幹線開業と南北接続で利便性向上等があげられる。
住宅地は前年同様、富山市と舟橋村で上がったほか、立山町がプラス0.9%となり、2003年以来20年ぶりに上昇に転じた。
富山市との隣接エリアで分譲地の開発が進んでいる影響とみられている。1㎡当たりの最高価格地点は、商業地が富山市桜町2丁目の56万8千円{2万6千円増・1坪187万4400円}で32年連続、住宅地が富山市舟橋南町の12万8千円{4千円増・1坪42万2400円}で35年連続、上昇率が最大だったのは、富山市牛島町の商業地域で6,9%である。
しかし、下がった地域もある。下落率が最大だったのは射水市新片町{新湊}の住宅地で3,7%だった。しかし、上昇は60地点で2022年度から10地点増えた。全国的には商業地の全国平均は1,4%,三大都市圏は4%のプラスで最高価格は東京都中央区の「明治屋銀座ビル」で1㎡当たり4010万{1坪1億3千233万円}で2019年以来4年ぶりの上昇である。
さて、資本主義社会では、「売る、買う」は需要と供給によって決まり、上昇や下落は当然であり、それぞれ功罪はある。故に、マスコミも今回は淡々と報道していたように思う。
そこで、司馬遼太郎が生前産経新聞「風塵抄」に月1回寄稿していた。平成8年2月12日付「日本に明日をつくるために」として掲載された文を少々長いが紹介する。実はこの日の午後8時50分73歳で亡くなった。まさに死の何日か前に書かれたものであろうが言わば「遺言」のようなものである。
「風塵抄――日本に明日をつくるために」 司馬遼太郎
「この世にはわからぬ事が多い。私の仕事は、古い書籍にかこまれていなければ,常在、不自由する。このため、東京オリンピックのあった昭和39年{1964}に、大阪の西区のアパートから、地価の安い東郊の外れに越してきた。早くいえば場末で、大阪市内であふれ出た家並みの東限になる。乱雑に家屋や木造アパートが建ちつつあった。
それらの低い建物にかこまれて、半段ほどの青ネギの畑があった。ときどき耕すとも見回るともつかぬ態度で、老農婦が姿を見せる。このひとは、法的に農地から宅地に転用されるまでのあいだ、青ネギを植えているいるのである。宅地に転用されれば、坪8万円になるという。法的には、体裁として栽培している。
あるいは、擬態として。さらにいえば半段の農地が大金を生みだすための時間待ちとして、1本5円ほどの青ネギをうえているのである。日本史上、はじめて現出したこの珍事象には、いままでの農業経済論も通用せず、労働の価値論もあてはまらない。労働のよろこびもなく、農民の誇りもない。
いかにえらい経済学者でも、この現象を、経済学的に説明することは、不可能にちがいない。青ネギが成長するころ、その農地は大願成就して、木造二階建アパートになり、そのころには、坪数十万円ぐらいになっていた。いかなる荒唐無稽な神話や民話でも、この現象の荒唐性には、及ばない。
これをもって経済現象と言えるだろうか。日本中が、そのようになっていた。物価の本をみると、銀座の「三愛」付近の地価は、先の青ネギ畑の翌年の昭和40年に一坪450万円だったものが、わずか22年後の昭和62年には、1億5千万円に高騰していた。坪1億5千万円の地面を買って、食堂をやろうが何をしようが、経済的にひきあうはずがないのである。とりあえず買う。1年も所有すればまた騰{あが}り、売る。
こんなものが、資本主義であろうはずがない。資本主義は、モノを作って、拡大再生産のために原価より多少利をつけて売るのが、大原則である。その大原則のもとで、いわば資本主義はその大原則を守ってつねに筋肉質でなければならず、でなければ亡ぶか、単に水ぶくれになってしまう。更には、人の心を荒廃させてしまう。
こういう予兆があって、やがてバブルの時代がきた。日本経済は――とくに金融界がーー気が狂ったように土地投機にむかった。どの政党も、この奔馬に対して、行手で大手を広げて立ちはだかろうとはしなかった。
なにしろ、バブル的投機がいかに妖怪であっても、困ったことに、憲法が保証する経済行為なのである。立法府も行政府も、法を基準としている以上、正面から立ちはだかるのは、立場上、やりにくかったのだろう。
しかし、誰もが、いかがわしさとうしろめたさを感じていたに相違ない。その後ろめたさとは、未熟ながらも倫理観といっていい。
日本国の国土は、国民が拠って立ってきた地面なのである。その地面を投機の対象にして物狂いするなどは、経済であるよりも、倫理の課題であるに相違ない。ただ、歯がみするほど口惜しいのは、「日本国の地面は、精神の上において,公有という感情の上に立ったものだ」という倫理書が、書物としてこの間、誰によってでも書かれなかったことである。
例えば、マックス・ウェバーが1905年に書いた「プロテスタンティズムと資本主義の精神」のような本が、土地論として日本の土地投機時代に書かれていたとすれば、いかに兇悍のひとたちも、すこしは自省したに違いなく、すくなくともそれが終息したいま、過去を検断するよすがになったに違いない。
住専の問題がおこっている。日本国にもはや明日がないようなこの事態に、せめて公的資金でそれを始末するのは当然のことである。その始末の痛みを通じて、土地を無用にさわることがいかに悪であったかを――思想書を持たぬままながら――国民の一人一人が感じねばならない。でなければ、日本国にあすはない」
これが全文である。
私には、このような名文は書けないが意とすることは理解できる。
資本主義とは、土地を無用にさわる事は、等かってのバブル崩壊から我々は多くの教訓を得たはずである。バブルとは膨れ上がった風船である、いつか破裂する。破裂した時が崩壊である。
平成8年前後と現在とは、社会情勢も経済環境もちがうから、同一には論じられない。あの時、県内のある金融機関も600億円を超す公的資金が投入された忘れることの出来ない苦い思いがある。基準地価が徐々に上がりつつある現在、バブル崩壊した時の教訓を思い起こすべきであろう。私の思いが杞憂に終わることを念じ――。
写真は、平成8年{1996}2月12日の産経新聞。