少にして学べば 壮にして為す 壮にして学べば老いて衰えず
老いて学べば死して朽ちず 佐藤一斎
11月28日{金}滑川市役所東別館で、滑川市中央公民館主催・福寿大学11月講座で「富山売薬の歴史から学ぶ」と題し1時30分から3時まで話しました。
この講座は昭和43年に開講され48年の歴史を持ち、月1-2回開催されています。対象者は基本的には60歳以上ですが、それ以外の方の参加も自由です。それにしても、昭和43年と言えば、まだ高齢化社会と言う言葉を耳にしない時代にこのような企画をされたことに驚きます。
当日会場では約80名ほど、また遠方の早月加積、東加積、山加積3地区はライブで配信され計30名程で合計約110名程の参加者でした。8月ごろ「滑川の売薬について」依頼を頂きましたが、売薬の町滑川で売薬のことを話しても、ご存知の方ばかりだから、とお断わりしましたが、最近、滑川でも売薬さんの後継者不足もあり、従事者数も減少しており、売薬の存在さえ知っている人が少なくなってきている。
だからと再度要請があり、お引き受けし、前述の演題となりました。
最初に
①現在・売薬の家。
②過去売薬であった。
③親戚が売薬であった。
に分けて挙手を求めたところ、いずれも僅かであった。
昭和55年滑川市教育センターが市内小学校高学年を対象にして副読本として発行した「滑川市の薬業」の小冊子を提示して、昭和54年市内の売薬さんは997人。それが現在では残念ながら2桁まで減少した。
そこで、話の内容は、人間は「衣食住」が満たされると、次の欲望は長寿、健康、薬であるから始まり,元禄3年{1690}2代富山藩主・前田正甫公が参勤交代で江戸城帝鑑の間に参集していた三春藩主・秋田信濃守が腹痛を起こし、正甫公が反魂丹を服用させたところたちどころに治った。
その効き目に驚いた全国の殿様がわが藩に是非その薬を、との要望に応え、全国に売薬が広がった。しかもその商法が「先用後利」であった。これが巷間伝わる売薬の起源である。その後、滑川には,享保18年{1733}高月村の千右衛門{高田清次郎家の先祖}が薬種商・松井屋源右衛門から「反魂丹」の製造法を習って屋号を「反魂丹屋」と呼び販売したのが滑川売薬の始まりであるといわれている。
また、明治の初め、堀江の伊藤某、松井某が「反魂丹屋」から製造方法を習い始めたのが堀江売薬の始まりである。そして、全国、九州から東北地方まで徒歩での行商や売薬が他藩の財政を圧迫すること、他藩の政治・経済などの情報が流失することを恐れ、藩内の出入りを禁止されるなどの困難を幾多の努力で乗り越え明治を迎えた。
しかし新政府は諸事西欧化に一新する事を政策の基本とし、医薬・医療制度も同様であった。明治3年{1870}「衛生上、危害を生じる恐れがある薬の販売を禁止し。有効な薬の製造を奨励する」との趣旨から「売薬取締規則」を発令し売薬の取り締まりに乗り出した。
当時「神仏・家伝・秘方・秘薬」の言葉を用い「万病に効く」といった余りにもいい加減な「妙薬」なるものが巷に野放し状態であった。この為、洋薬礼賛・漢方排斥を第一とする維新政府の考えから、漢方薬などと共に富山売薬のきっちりとした和漢生薬の薬も巷のまがい物の薬と同様に見られた。
明治4年{1871}それまで売薬が取り扱っていた約100品目が、熊胆丸・奇応丸・一角丸・紫金錠・万金丹・反魂丹・感応丸の僅か7品目に限定された。業界は一致団結し、規制緩和の陳情をする一方、売薬業者たちは従来の家内工業的な製造方法から品質確保に重点を置いた良質な医薬品製造に向け大同団結し、それぞれの特色を生かし、かつ漢方の良さを残しつつ洋薬に対応した新会社を設立する。これが明治9年{1876}現在の廣貫堂である。
しかし新政府により明治10年{1977}「売薬規則」による売薬税が制定され、売薬営業税、鑑札税が課された。これは新政府が戊辰戦争、明治7年{1874}佐賀の乱から秋月の乱、萩の乱、神風連の乱、そして明治10年{1877}西郷隆盛との西南戦争である。これらに要した膨大な戦費の支出の為、あらゆる分野に増税を課した。
そして明治16年悪名高き「売薬印紙税」が施行される。現在の消費税のようなものである。
例えば、定価一銭から10銭までは一銭の印紙を製品に貼り付けすることが義務付けられた。定価が高くなるにつけ印紙税も高くなるのである。ご存知の通り、売薬は「先用後利」の商法で、薬を置いた時は無料で、次回訪問時使用分のみ代金を頂くシステムである。薬品は仕入時全ての製品に印紙を貼り付ける為、この手間と使用しなかった薬品に貼り付けた印紙税代が売薬業者の負担となった。
この打撃は深刻で、明治15年{1882}売薬の生産額は672万円、行商人9700人が税施行後、明治18年{1885}生産額50万円,行商人5000人まで激滅した。印紙税撤廃陳情を重ねる中、未使用の製品に貼り付けた印紙は回収後、同額の新品の印紙と交換されることになった。この税が廃止されたのは大正15年である。
しかし「売薬印紙税」は海外売薬には免除されたことから、明治18年{1886}藤井論三がハワイで配置売薬を始めたのを皮切りに,韓国へ,清国へ、そして寺田久蔵や笠松佐平が上海へと飛翔、その後中国大陸、台湾、ウラジオストック、樺太、さらに遠くブラジルなど、富山売薬は日本人の行く所どこへでも進出していった。滑川の先人は台湾売薬が主であった。
また、専門知識を持つ人材の育成にも力を注ぎ、明治26年{1893}売薬業者により共立富山売薬学校を設立し、これが明治30年{1897}富山市立となり、明治39年{1906}県立薬学校になり、大正9年官立薬学専門学校、いわゆる薬専となり、それが現在の富山大学薬学部となり、製・販の近代化と資質の向上に大きな役割を果たしてきた。
また、忘れてはならないことに明治の富山県の近代化は薬業人の手によって成し遂げられたことである。現在の北陸銀行も北陸電力などの金融・電力も薬業人の投資によって起業され、売薬業が盛んになることによって、他産業、印刷・製紙・ガラス産業・紡績など幅広い分野に投資し、今日の富山県発展の基礎を築いたのである。滑川でも滑川売薬信用組合が滑川信用金庫になり現在のにいかわ信用金庫になっているのである。
このようなことを話し、富山売薬のエピソードを紹介した。
①江戸・天保年間{1830-1844}に大阪で作られた資料では、全国の著名薬46種の番付けで富山の「越中反魂丹」が京都の「雨森無二膏」伊勢の「朝熊萬金丹」奈良西大寺の「豊心丹」などを抑え第一位にランクされている。
②売薬に必要な読み・書き・ソロバン取得のため富山では教育が盛んになり、明和3年{1766}富山の西3番町に開かれた寺子屋「小西塾」は、日本三大寺子屋と称されるほど大規模で、今日の教育県富山の原点はここにあること。
③富山の薬売りを顕彰する石碑{酬恩碑}がある。「青木伝次」は農業に従事するかたわら農閑期に富山の薬売りとして、現在の山形県米沢市塩井町を行商の折,備中鍬で苦労して田を耕す村人たちを見た。伝次の地元富山では既に馬を使った馬耕法が広まっており、その技術を教えようと、明治32年に富山から馬耕機を持参し、その使い方まで指導した。馬耕機は伝次と地元の鍛冶屋で改良が加えられて更に便利になり、置賜一円に広まって農家の重労働を軽減させました。村人は伝次を先生と慕い、明治34年{1901}に石碑を建て感謝しました。これは米沢市「広報よねざわ」平成26年12月1日発行に掲載された文を紹介し、全国にこのような話や仲人の話など幾つもある事を話しました。
④廃藩置県が断行された明治4年{1871}の人口調査の資料では、富山は全国9位に位置していた。69万人の東京をトップに2位大阪が29万人・3位京都が23万人・4位名古屋・金沢10万人台・6位広島8万人台・7位横浜・和歌山6万人台・次いで、仙台と並んで9位に5万人台の富山がある。「富山売薬」という一大産業によるものであろう。
このようなことを話し、最後に富山売薬が300年以上存続してきたのは、単に先用後利の商法だけでなく、色々なことを勉強していて話題が豊富で薬を届ける以外に田畑の作り方を指導したり、全国各地の文化や情報の伝達者であったことが挙げられる。
一軒一軒の家を訪ね、その家の人の「顔」と「生活の場」をしっかりと見て、顧客を「個」で捉え、「個々」に対応してきたことが大きな要因で、売薬に見る富山気質は「信用第一」「薬効第一」「顧客第一」に徹したことである。
かって富山大学教授・植村元覚氏は富山県薬業史の中で、17世紀のフランス人で経済学者ジャック・サバリーの言葉を引用して、「完全な商人」とは㋐信用・信頼性 ㋑良い商品 ㋒市場調査 ㋓記帳と経理である。
この四つの項目を富山売薬商人の商業に当てはめるとそれは見事に一致する。
300年の長期間にわたって、全国行商を続けてくることができたのは、正にこの点にある。と記しておられる。このように、苦難の連続であった富山売薬の歴史を紐解くと「まごころ」があり、「したたかさ」があり「知恵」をもってその時々の社会の変化に対応してきた。
歴史の中に、未来に花咲く種子が沢山あることを話し1時間半を終えた。
写真は、パンフレット、講演会風景。
![251128152756334[2]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/11/2511281527563342-759x1024.jpg)
![251128133730773[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/11/2511281337307731-1024x759.jpg)
![251128133508519[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/11/2511281335085191-1024x759.jpg)
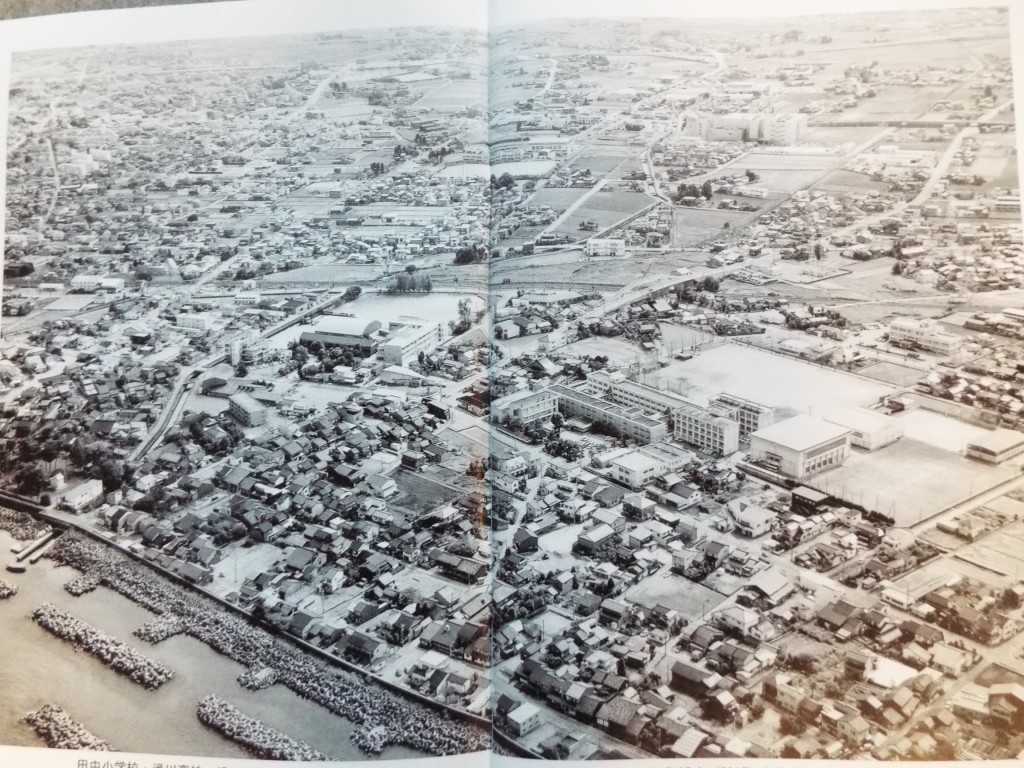
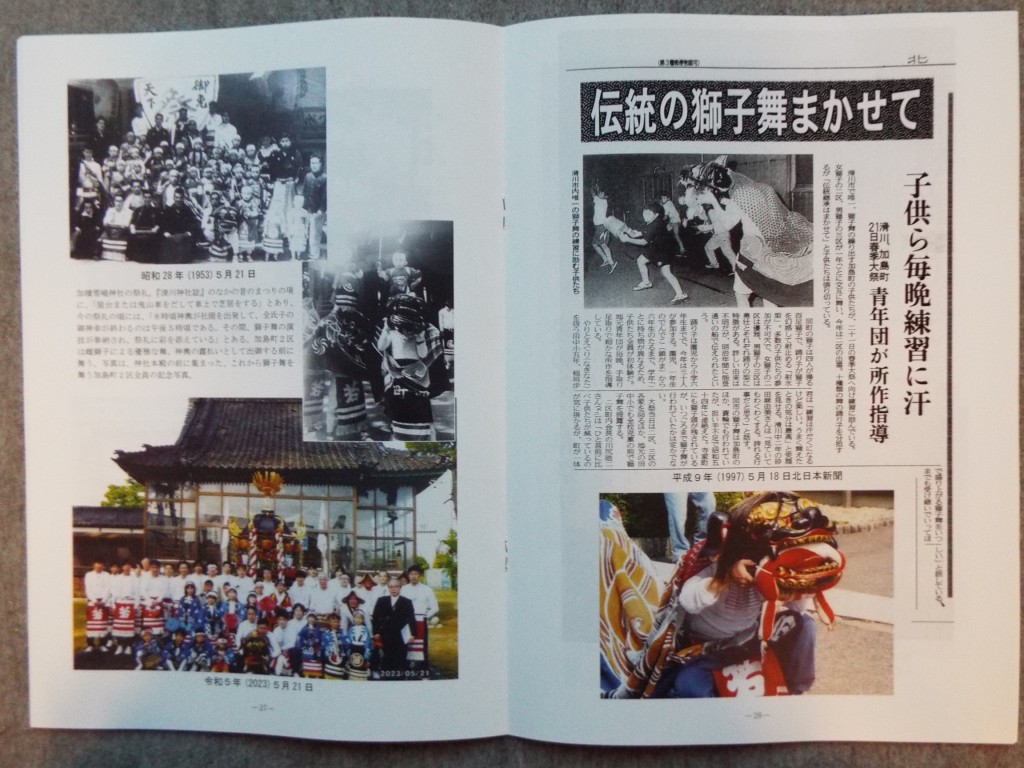
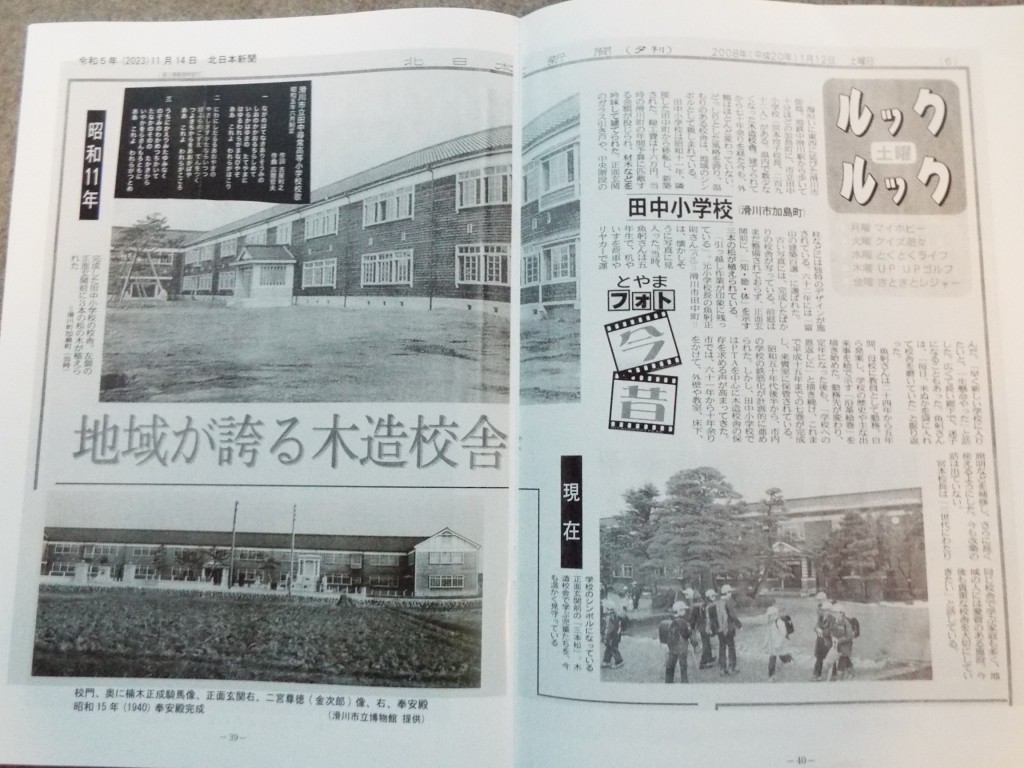
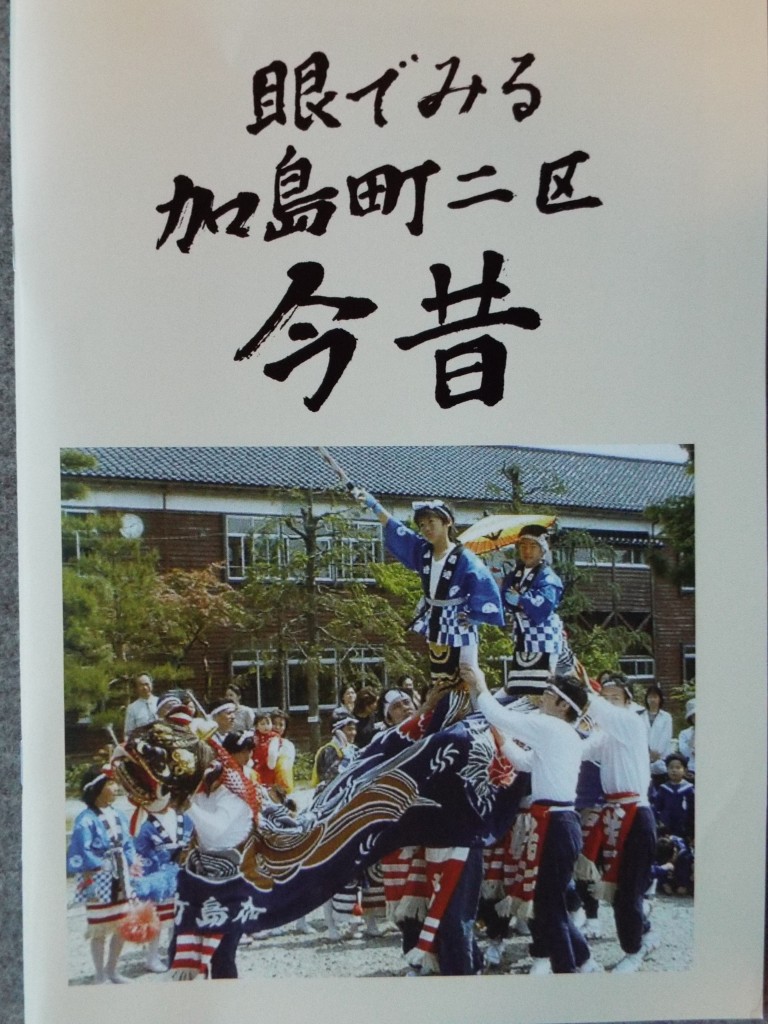
![251128152756334[2]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/11/2511281527563342-759x1024.jpg)
![251128133730773[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/11/2511281337307731-1024x759.jpg)
![251128133508519[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/11/2511281335085191-1024x759.jpg)
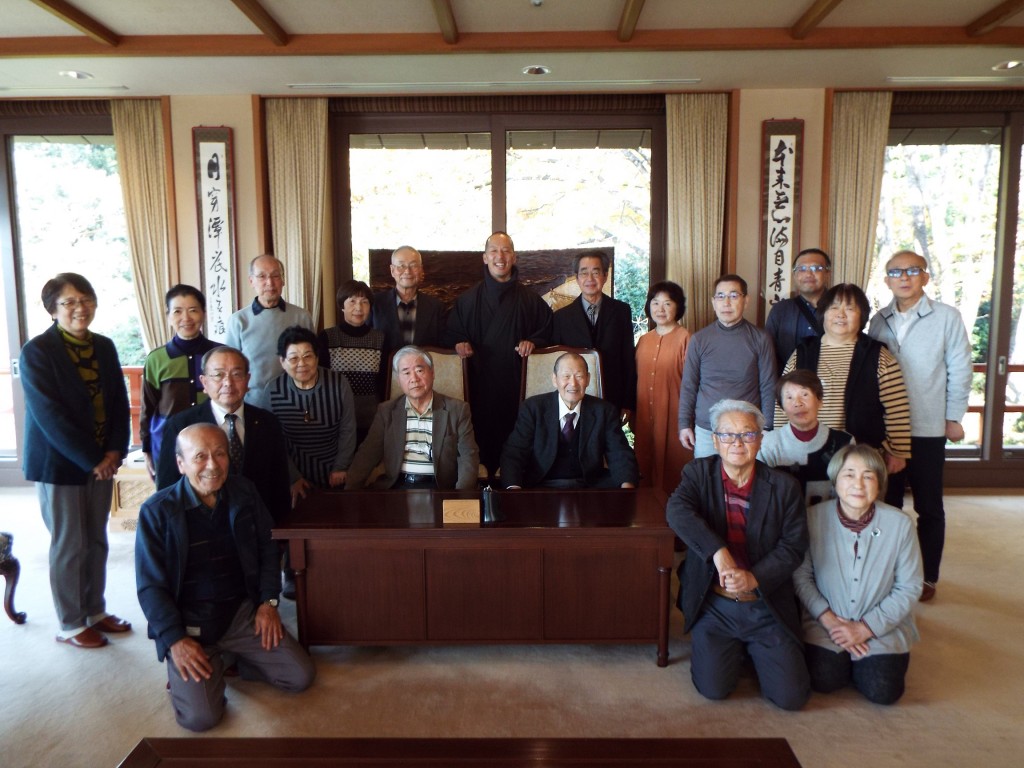



![251122101429297[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/11/2511221014292971-1024x759.jpg)
![251122125309265[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/11/2511221253092651-1024x759.jpg)
![251112121258571[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/11/2511121212585711-1024x759.jpg)
![251112135520873[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/11/2511121355208731-1024x759.jpg)
![251106105820933[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/11/25110610582093311-1024x759.jpg)
![251106111147747[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/11/2511061111477471-1024x759.jpg)
![251106112459339[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/11/2511061124593391-1024x759.jpg)
![251106112440846[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/11/2511061124408461-759x1024.jpg)

